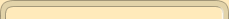開店10分前。ガラガラと店の戸が開き、一人の客が入ってきた。「もう、いい?」。どうやら常連のようだ。それを皮切りに、待ってましたと言わんばかりにたくさんの客がなだれ込んだ。「いちご大福10個、豆大福5個、それと串団子5本」。2個や3個ではない。数々の商品が並ぶショーケースを前に、10個や20個まとめて買い求めて行く客が少なくない。そんな店内の様子を見て、すぐ奥の部屋に戻り製造を再開したのは、職人歴25年、「二幸」3代目の、久保幸雄さんだ。  看板商品の「いちご大福」は昼前に完売してしまう日があるほど人気。新鮮ないちごをなめらかなこしあんで覆い、さらにそれを鮮やかなピンク色の餅が包む。餅の柔らかさ、あんの甘さ、いちごの甘酸っぱさが三味(位)一体となって口の中に広がる。釧路の人間であれば、一度は口にしたことがあるのではないだろうか。地元住民だけではない。道内、道外から訪れた人々も、口コミを聞きつけ立ち寄る。「二幸」の人気菓子というだけではなく、もはや釧路を代表する菓子となった。 久保氏は、小学生の頃から店でお菓子の箱詰めなどを手伝っていた。日々お菓子に触れ、いつしか将来自分も菓子職人の道に進むんだとの自覚が芽生えていた。釧路の高校を卒業後、東京の製菓学校に進み、卒業後はそのまま東京・赤坂の和菓子屋に勤めた。当時の赤坂には多くの料亭が建ち並び、そのどまん中にあった勤務先には毎日たくさんのおつかい物の注文が入った。製造の技術を学び、毎日多くの作業をこなすことによって自信をつけた。釧路の実家「二幸」へ戻ったのは、それから5年後のことだった。 最も忙しい街で仕事をしてきたという自負があったが、それは早々に打ち砕かれた。そのときの衝撃を今でも覚えているという。おつかい物だったお菓子は、干菓子であるお茶菓子や焼き菓子が中心だったが、実家で作っているのは生菓子の餅やまんじゅう。簡単に応用できるかと思っていたが、甘かった。2代目である父や、長年従事しているパートさんにおしえてもらいながら、一からお菓子作りを学んだ。本領を発揮できずくやしい気持ちはあったが、人生の中で無駄なことはひとつもないんだと気持ちを鼓舞させた。  毎日同じものを作っているつもりでも、ちょっとした違いでそれは同じものではなくなる。餅の堅さは、使う餅米などの材料だけでなく、作り方やその日の気温にも左右される。常々通う客は“この間食べたものと同じもの”を求めてまた来店するので、餅は堅くても柔らかくてもだめ。作り続けるほどにそういった細かな調整はできるようになったが、未だに召し上がっていただくお客さんのほうが敏感だと言う。 2店舗目を出せばいいのに、との声も多く上がる。なぜ出店しないのですかと問うと、「ありがたい話だけど、目の届く範囲でやっていきたいから」とのこと。繊細な餅を扱うことの大変さを十二分に理解しての回答。今日も“変わらない味”を食べることのできるわたしたちは、なんて幸せなんだろうと感じた。 |